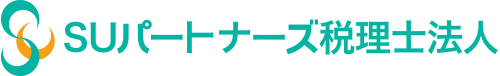相続・事業承継Vol.63 配偶者居住権の活用 後編 -なぜ配偶者居住権を利用するのか-
配偶者居住権の活用 後編 -なぜ配偶者居住権を利用するのか-
相続・事業承継Vol.63
皆さんこんにちは。SUパートナーズ税理士法人の露谷です。
前回(相続・事業承継Vol.62)に引き続き配偶者居住権の活用に関するお話をさせて頂きたいと思います。
前編では「配偶者居住権」の活用の意義についてご説明させて頂きましたが、実際に利用してみようとなった場合にどこで何をすればいいのか、という疑問が生じます。
また、「配偶者居住権」を活用する事によって相続税の申告にも影響を及ぼす事になることに注意が必要となります。
そこで今回は利用する際の手続きや税制面などの細かい論点をご説明させて頂きます。
・「配偶者居住権」の設定と手続き
まず「配偶者居住権」の設定についてです。
これは当然なのですが『ここは配偶者居住権のある物件です』と他人に公言をしてもそれが法律上約束されるものではありません。
法律上で認められる為には「配偶者居住権」を設定したい物件(自宅)の所在地を管轄する法務局へ赴き「登記」といわれる事務手続きをする必要があります。
手続きをする際にはいくつかの必要書類があることに注意が必要となります。
身分証明書や印鑑証明書などがこれに該当しますが、最も重要なものは相続発生時に作成が必要となる「遺産分割協議書」という書類となります。
この「遺産分割協議書」が未作成の場合では、例え配偶者自身の申請であっても「登記」を認めてもらう事ができません。
・「遺産分割協議書」ってなに?
「遺産分割協議書」とは遺産を相続する際にその財産について相続人がどの財産を相続するかのを記載した書類の事をいいます。相続人同士が協議を行いその全員が同意し署名捺印を行う事が必要となるため作成には時間を要しますが、その効力はとても強く「登記」などの様々な手続きに欠かせない重要な書類となります。
今回議題となっている「配偶者居住権」を相続する場合にもこの「遺産分割協議書」に『配偶者』が『配偶者居住権』を『相続する』といった文言を記載する必要があります。
そしてその「遺産分割協議書」が証明書類となり「登記」などの手続きを行えるようになります。
・「登記」を設定するための手数料
また、「登記」を行う場合には上記で説明した複数の書類が必要となる他に登録免許税と言われる手数料が必要となります。
「配偶者居住権」の場合は基本的に固定資産税評価額の1000分の2の手数料が発生します。評価額が高い資産の場合だと数万円~数十万円の出費となるため軽視できない出費となりますので十分にご注意してください。
ここまでが手続きに関するご説明となります。
実際の相続ではこれらの手続きがスムーズにいかないこともありますので、事前に信頼できる税理士や司法書士にご相談する事をお勧めさせて頂きます。
次に税制面でのご説明をさせていただきます。
・税制面での有用性は?
「配偶者居住権」は相続の際には「建物に関する権利」と言われる財産として判定され、居住権の対象となっている居住用建物の相続評価額を基礎として存続期間等の複利現価率を乗じて評価額を算定する事となります。
この計算自体はとても複雑なため実際には申告書を作成する税理士が計算をする事となりますが、基本的には本来の居住用建物の相続税評価額を超える事はありません。
また、この居住権の対象となっている居住用建物の敷地の用に供されている土地については『小規模宅地等の課税価額の計算の特例』が適用できます。
この特例を利用すれば評価額を大幅に減額する事が可能となるので税制面ではとても有利なものとなります。
ただし、居住用の場合はその減額を受ける事ができる土地の面積が330㎡までであること、その「配偶者居住権」の対象となっている建物の一部が別の用途に使用されている場合にはその一部に対応する土地の部分は小規模宅地等の特例が適用できない事などに注意が必要となります。
こちらも「配偶者居住権」の建物の状況によりその処理方法が大きく変わってしまう事例となるため利用の際には担当の税理士と十分な相談をしておく事が重要となります。
如何でしたでしょうか。
やはり手続きや税務面となると少しややこしく見えるかもしれません。
ですが、そこは専門家にお任せすればいいものでもあります。
「配偶者居住権」について少しでも興味を持って頂き将来に活用して頂ければと思います。