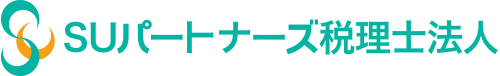国際税務Vol.38 国が敗訴?居住者判定の新潮流
国が敗訴?居住者判定の新潮流
国際税務Vol.38
皆様こんにちは。
他の先進国と比較して日本は税務当局の力が強く、裁判になっても納税者側が勝訴することはめったにありません。ただ、たまに驚くような展開で納税者が勝利する場合があります。ここで非常に珍しい事例の一つをご紹介したいと思います。
年間の大半をシンガポールなどの複数の国で過ごしていた法人の代表者が、所得税法上の「居住者」と「非居住者」のいずれに該当するかについて争われていた事件について、東京高裁は、当該代表者は「非居住者」に該当すると判断しました。
その後国は上告を断念し、納税者の勝訴が確定しました。(東京高裁 令和元年11月27日判決(行コ)第186号)
居住者と非居住者とは
日本の所得税法上、「居住者」とは
国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。なお、一定の場合には、その人の住所がどこにあるかを判定するため、職業などを基に「住所の推定」を行うことになります。
複数の内国法人と海外法人の代表を務めるA氏は、日本、アメリカ、シンガポールにそれぞれ年間100日前後滞在していました。シンガポールに設立した会社はヨーロッパ、中東、オセアニアなど世界の市場を対象としており、A氏はそれらの会社の重要な意思決定に関与していたため、各国へ頻繁に出張していました。
A氏は日本に約2億円の預貯金、投資信託口座や代表を務める法人の株式、母と共同で居宅や自動車を保有しており、生計を一にする妻ら家族は日本に居住、A氏本人の住民登録については転出届をしていませんでした。
裁判所はA氏の住所の判断にあたり、「滞在日数、住居、職業、生計を一にする配偶者その他の親族の居所、資産の所在等を総合的に考慮して判断するのが相当である」と判断しており、上記の事実から以下のような判断をしています。
滞在日数について A氏が住所地と主張するシンガポールの滞在日数と日本の滞在日数に大きな差はなく、日本、アメリカ、シンガポールを起点とする渡航先国での滞在日数を加味した上で原告の生活の本拠が日本国内にあったことを積極的に基礎づけることはできないと判断しています。すなわち、各国への渡航の利便性が高いシンガポールを拠点とする他国への短期渡航はシンガポール滞在と実質的に同一視する方が実態に適合するという見解を示したのです。
職業について A氏の日本における業務が各社の代表取締役社長として毎月1回の経営会議や年2-3 回程度の株主総会、取締役会に出席するほか、重要な意思決定については相談を受ける程度のものであったのに対し、各海外法人については経営判断は専らA氏が行っていたものであり、自らが現地へ赴く回数も多数に上ったことを認定しています。
家族の居所について A氏の妻や二女は日本居宅において居住を続けていましたが、年間の大部分を海外の各地で過ごすA氏の職業活動に適応した生活の在り方として、妻らの生活の本拠は海外に移さず、A氏が帰国した時に休暇も兼ねて妻らと会うという方法を選択したものということができるので、妻らが国内に居住していたことはA氏の生活の本拠が日本国内にあったことを積極的に基礎づけるものとはいえないと判断しています。
資産の所在について A氏は国内に多額の資産を有しているが、シンガポールにも1700万円以上の預貯金があり生活に十分な額の資産を有していて、日本の預貯金をシンガポールへ移転していないことは家族を残して海外に赴任する者の行動として不自然ではなく、日本により多くの資産を有していることをもって生活の本拠が日本になったことを積極的に裏付けるものとはいえない、と判断しています。
その他 A氏は日本住所地における住民登録の転出の届け出をしていませんでしたが、これについてA氏は各社の借入に係る個人保証の手続き等において印鑑登録証明書を取得する便宜のためだと説明しています。一般に適切な届出がされず住民登録の所在が必ずしも生活の実体を反映したものとなっていない例があることや、海外に赴任する者が他の手続き上の便宜のために日本国内に住民登録を残しておくことも不自然であるとは言い難く、転出届をしていなかったことをもって生活の本拠が日本にあったことを積極的に基礎付けるものとはいえないとしています。
このように今回は総合的な観点からの判断となっており、今後の指針となる重要な判例となっています。同様の争点の事案が今後も増加していくことが予想されるため、ぜひとも参考にし、実務対応したいところです。